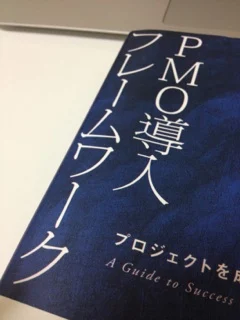最近、自分の根性を出して事を成す、という発想を忘れていたなあ・・・
と思い、このエントリを書いています。
自己啓発書には、3日坊主になりがちな人向けに、「ものごとをいかに続けるか」といった工夫があれこれ書いてあります。
例えば、英語を勉強している人は、
「英語を一緒に勉強する友達を作れ」
「英語を勉強していることを公言しろ」
「とにかくTOEICに申し込んでしまえ、会社に点数が知られるくらいが好ましい」
「点数アップしたら、自分にご褒美を与えると決めろ」
とかですね。
こういう工夫をたくさんして、英語を勉強せざるを得ない環境を作り出せという発想です。
私もこういった工夫を大いに取り入れてみたし、メリットもすごくありましたが、最近少し考え方を見直しました。
こういうことをやり過ぎると、なんか生活が複雑になる気がします。
それに、目的を失ったアクションが習慣として残るのも嫌です。
「とにかく仕組みを作る」という発想でいると、何か失敗してしまったときも、「まず仕組み」と思ってしまいます。
それよりも、自分の根性だけで続けられるなら話は早いです。
最近、この「自分の根性で強引にやる」という方向を忘れていました。それに、目的を失ったアクションが習慣として残るのも嫌です。
「とにかく仕組みを作る」という発想でいると、何か失敗してしまったときも、「まず仕組み」と思ってしまいます。
それよりも、自分の根性だけで続けられるなら話は早いです。
ということで、
「仕組みよりもまず根性」
という精神を取り戻します。
仕組みがダメとは考えません。
仕組みもOKだけど、まずは根性ということです。
などと書きつつ、共感を得られる話なのか全く分かりませんが。
尚、会社みたいに大勢が集まる環境では、これは全然当てはまらないと思います。
「根性より仕組み」に、大いに賛成です。