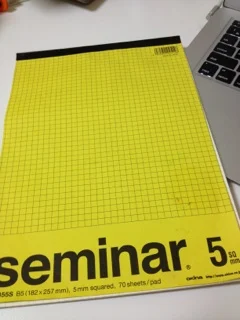先々週から、「iPadプレゼンセミナー」というのを受講しています。
全5回のうち2回が終わりました。
全5回のうち2回が終わりました。
実はiPad自体にはそれほど興味が無かったのですが(一応持ってるけど)、会社がPowerpoint文化になってきたので、スライドを使ったプレゼンテーションの技を増やしたく受講しました。
本講座で推奨しているプレゼンテーションのスタイルは「シンプルプレゼン」。
スライドには大量の文字を書かずに、1行とか、3行しか書かない。残りはプレゼンテーターの喋りで話を進めていく、というやり方です。
例えば、スティーブ・ジョブズのプレゼンテーションは、スライドがものすごくシンプル。例えばiPhoneの写真を1つ映したまま、ジョブズがベラベラ喋ります。主役はあくまでジョブズ。
例えば、スティーブ・ジョブズのプレゼンテーションは、スライドがものすごくシンプル。例えばiPhoneの写真を1つ映したまま、ジョブズがベラベラ喋ります。主役はあくまでジョブズ。
これに対して、日本の企業で多いのが、スライドに説明文書をガンガン書くやりかた。主役はスライド(=説明書)。
(動画はジョブズがiPhoneを紹介するプレゼンです。最初の3分10秒くらいまでが特にかっこいい。)
(動画はジョブズがiPhoneを紹介するプレゼンです。最初の3分10秒くらいまでが特にかっこいい。)
面白いと思ったのは、前者の「シンプルプレゼン」はプレゼンテーターが主役なので、プレゼンテーターごと売り込めるということ。
そういえば、ジョブズもプレゼンテーションで名をあげましたよね。
スライドを主役にするのではなく、あくまで主役はプレゼンテーター。
なるほど、個人を売り込むのには使える考え方かもしれないし、これならiPad関係なく応用できますね。
スライドを主役にするのではなく、あくまで主役はプレゼンテーター。
なるほど、個人を売り込むのには使える考え方かもしれないし、これならiPad関係なく応用できますね。
私の勤め先では、プレゼン資料はどちらかというと説明書なので、会社で全スライドをこのように作るのはハードルが高いですが、プレゼンテーションの途中で2~3枚混ぜることは出来そうです。きっとメリハリがついて良いだろうと思います。
今度やってみよう。
新しい技を身につけるのは良いですね。
今度やってみよう。
新しい技を身につけるのは良いですね。
ちなみに、受講しているうちにiPad自体の面白さにも気付いてきましたが、それは多分また今度。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なお、このセミナーは、去年「スピーチ・プレゼンセミナー」を受講したのと同じ、日本プレゼン・スピーチ能力検定協会の講座です。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
なお、このセミナーは、去年「スピーチ・プレゼンセミナー」を受講したのと同じ、日本プレゼン・スピーチ能力検定協会の講座です。